専門コラム「指揮官の決断」
第429回危機管理の視座 その3
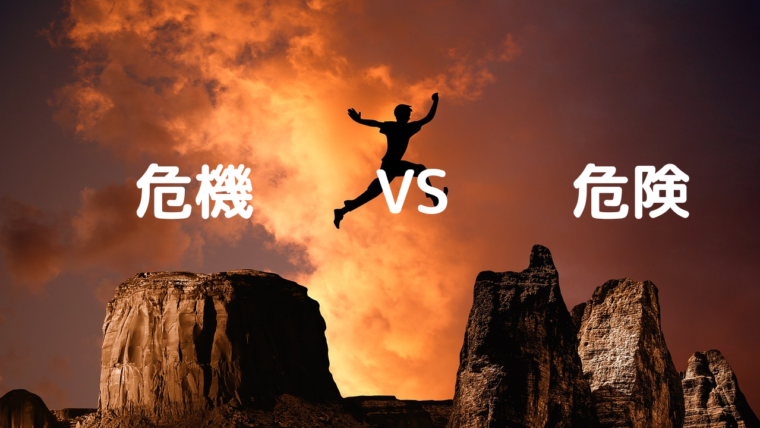
政治家にとっての危機管理
2回にわたって、この国では危機管理の概念が理解されておらず、リスクマネジメントと同義だと考えている人たちが多いことに言及してきました。
政治家たちは、危機管理を「最悪の事態を想定して、それに備えること」という解釈をするのですが、それは、彼らにとってその解釈が都合がいいからです。
誰にとっても想定外の事態が生じた場合には、責任を問われないからです。想定外だから仕方がないということになるので、政治家は責任を追及されません。
政治家にとって、もっとも都合が悪いのは、責任を取らなければならなくなることです。
マスコミにとっての危機管理
一方のマスコミにとって危機管理の概念などはどうでもいいことです。彼らは世の中が不安になれば、それを煽ることによって視聴率や購読率を稼ぐことができるので、「危機」だろうが「危険性」だろうが関心がないのです。
彼らは、ただ「危機管理が甘い、できていない。」と批判していれば済みます。
その典型が、最近亡くなったみのもんた氏の熊本地震に際してツイッターへの投稿です。彼は「今回の震災もね、熊本だけじゃなくて九州全体だから。支援のやり方も甘い。自衛隊きちんとして欲しいね。あと、過去の震災、阪神淡路、もっと遡れば関東大震災の教訓活かせてないでしょ?…みたいにTVではちょっと言いづらいことも、ここでは言いたいね」と呟いたのです。
どのような教訓をどう活かしていないのかについて、論理的な説明はまったくなく、ただ、批判をしただけです。
メディアにとっては「危機管理」だろうが「リスクマネジメント」だろうがどうでもよく、単にそれらの言葉を使って報道ができればいいらしいので、阪神淡路大震災の頃、当時としては新しい言葉であった「リスクマネジメント」という言葉をその意味を大して考えずに使ったのです。この辺の事情については、このコラムで言及してきましたし、近々、再度触れていきます。
メディアは、とにかく新しい言葉やちょっと変わった言葉を使いたがります。そこで自分たちの差別化を図ろうとしているのでしょう。
当コラムでは、ある新聞が「コンプライアンス」と言う言葉を使うたびに、その後ろにカッコを入れて「コンプライアンス(法令遵守)」と記述することを指摘したことがあります。
ちなみに、“compliance”に「法令遵守」という意味はありません。むしろ、法の網を潜り抜けるような行為はコンプライアンス違反となる恐れが大きいとさえ言えます。この新聞は、コンプライアンスという言葉は使いたいのですが、その意味するところは知らないようです。
昨年の能登半島の地震被害に際しては、メディアは「兵力の逐次投入」という言葉を使いたがりました。これは軍事用語で、一般にはあまり使われない珍しい言葉なので、メディアが得意になって使いたがりました。
能登半島における地震災害に際し、陸上自衛隊の災害派遣兵力が日を追って増えたいったことを批判したものです。熊本地震の時の初動と異なる勢力に眼をつけたメディアが「兵力の逐次投入」という軍事用語を使って報道したのですが、能登半島地理的条件を考えれば、一挙に大兵力を集中して、多数の車両が動き回ったら、主要道路が隆起陥没で使えなくなっている状況で、消防車も救急車も動けなくなることは自明であり、「逐次投入」ではなく、「段階的投入」と云うのが正しいのですが、マスコミは、とにかく珍しい言葉を使えればそれでいいのでしょう。
この国の危機管理の概念がどうなろうと彼らが責任を問われるわけではないからです。
当コラムが考える「危機」と「危険」
ただ、危機管理の専門コラムが、危機管理の概念を誤って理解することはできません。
少なくとも、このコラムをお読みいただいている方々には正しく理解していただく必要があります。
問題は、「危機管理」とは何か?という問いを投げかけると100人いると100通りの答えが返ってくることです。
物理法則は、ある一定の条件の下では普遍的な法則が妥当します。
重力のある場所では、モノは支えを失うと移動します。移動していく方向が「下」であり、このことをモノは上から下へ落ちると表現します。
社会科学ではそのような厳密性を問えないものが圧倒的多数です。
そこで、危機とは何かということを最初から考えなければなりません。
まず、危機の特徴から考えます。
個人・組織・社会などに具体的な損害を与えるという特徴を指摘できるでしょう。
損害が全くなければ、それは「危機」とは言われないはずです。
そして、ある時、突然生じ、そして対応にそれほど猶予がないということも特徴と言えるかと思います。
東日本大震災や能登半島の地震などは、専門家は予測はしていましたが、具体的な日時が予見されていたわけではありませんし、地域住民や自治体、政府にとっては「元旦」にいきなり生じた災害であったはずです。
たとえば、大きな惑星が地球に衝突するコースで宇宙空間を移動している場合、それが発見されてから、衝突までの時間はかなりあるのでしょうが、避ける手立てがない限り、時間的猶予があるとは言えませんので、それも重大な危機でしょう。
つまり、想定外の、個人・組織・社会に大きな損害を与える事態で、対応する時間的余裕がほとんどないものが危機であると云うことができそうです。
一方のリスクマネジメントのリスクですが、これは危険性を指しています。
辞書をひいていただけば分かりますが、”risk”に「危機」という意味はありません。「危険」もしくは「危険性」という意味が示されています。
危険というものは、危機とは異なり、何がなんでも避けなければならないものではありません。必要があれば、それを利用することもあります。
たとえば、危険物です。発火性が強かったり、毒性が強かったりする危険物はたくさんありますが、それぞれがいろいろなものを作ったり、動かしたりするのに重要な役割を担っています。
ただ、素人が扱うと危ないので、しっかりとした資格を持った人に扱ってもらう必要があるので、免許制度が作られています。
医師や看護師、薬剤師など医療関係だけでなく、船舶や航空機の運航なども素人には任せられません。
しかし、危険だからと言って、手術をしないわけにもいかず、薬を調合しないと患者も困りますし、海難の恐れがあるから船舶の運航をしないとなると物流が途絶えます。墜落の恐れはあるかもしれないが、やはり航空機の運航は現代社会には必要です。
つまり、危険というのは、そういうものです。ある程度危ないかもしれないが、注意して扱うことにより、その便益を享受するべきであったり、必要な措置を取るためには、それなりの危険性も受け入れる必要があるという場合は少なくありません。
しかし、その危うさや危険性が現実になった場合の対応はあらかじめ準備しておく必要があるということで、リスクマネジメントが重要なのです。
これを要するに、危機は、想定外の、対応にあまり時間的猶予を与えられない事態をいかに防ぐか、あるいはそのような事態が生じた場合の対応が課題とされるのに対し、リスクは、想定し、どこまでそのリスクを受け入れるかを判断し、そのリスクが現実になった場合にはどうすべきかをあらかじめ準備するということが重要だということです。
危険性と危機の違いが分からぬ男にこの国の命運を託してはいけない
そこで、岸田前首相が「危機管理の要諦は、最悪の事態を想定し、それに備えること。」という考え方が、根本的に間違いだということが分かります。
つまり、彼は危機管理の概念をまったく理解していないのです。
ただ、政治家で、危機管理の概念を理解しているという者を見たことがありませんので、彼だけが特別ではありません。
政治家は、想定外の事態への対応について責任を問われるのが嫌なので、危機管理を最悪の事態を想定することから始めるのですが、想定できるなら危機管理ではありません。
それはリスクマネジメントです。
しばらく、その危機管理とリスクマネジメントの概念について深堀していきます。


